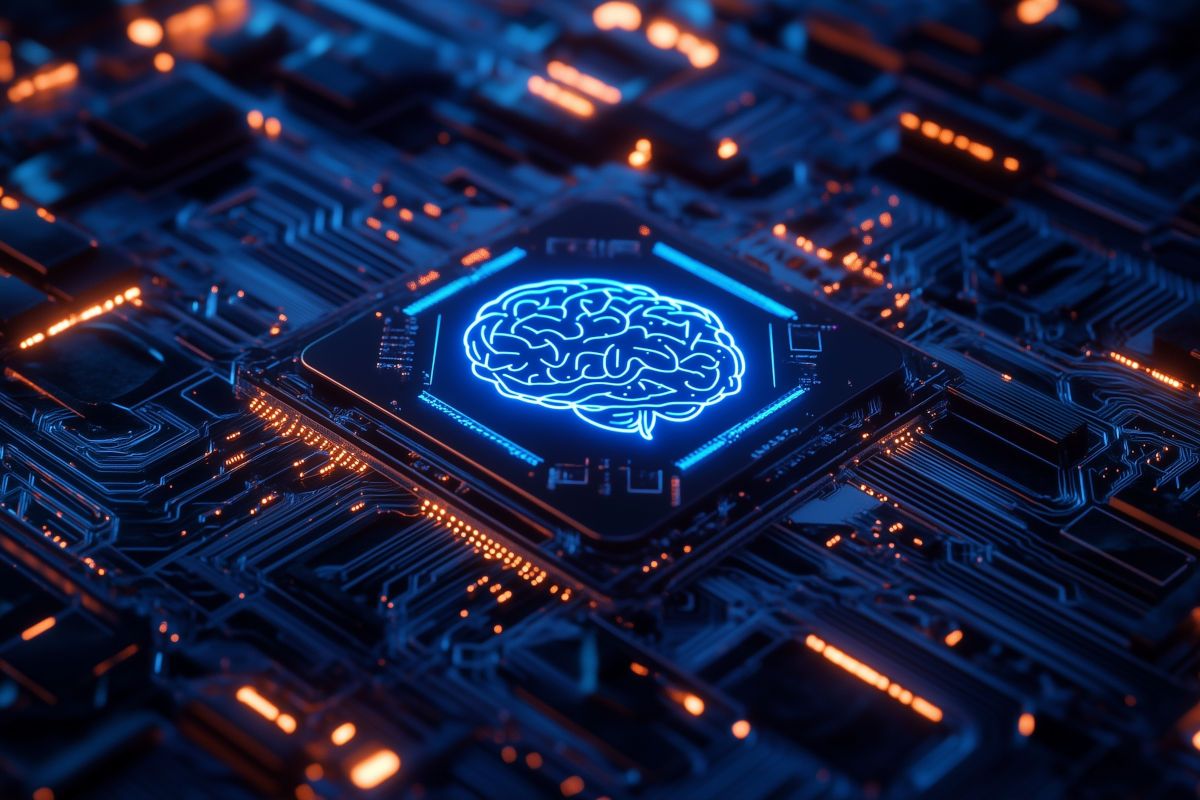数十年にわたり、
科学者たちは脳のように振る舞う
電子回路を作ろうとしてきた。
この発想はニューロモーフィック・コンピューティング
(neuromorphic computing)と呼ばれ、
現在主流のプロセッサーに頼るのではなく、
脳内のニューロンが発火し結合する仕組みを
模倣するようチップを設計するものである。
期待は大きい。
人間により近い「考え方」をしながら、
消費電力ははるかに小さいコンピューターなのだ。
しかし問題は、
人工ニューロンが実際のニューロンと同じ
電圧レベルでやり取りしないことであり、
これが能力の限界となっている。
マサチューセッツ大学アマースト校(UMass)のチームが、
このギャップを埋めたかもしれない。
同チームの人工ニューロンは、
生細胞と同じ電圧範囲で発火し、
1回のスパイク当たりピコジュール単位の
エネルギーしか用いない。
この成果はNature Communicationsに掲載され、
シリコンと生物がついに同じ
「電気の言語」で会話できることを示した。
微生物ナノワイヤ vs. シリコン
UMassのデバイスの中核はメムリスタ(memristor。
メモリーとレジスターを組み合わせた造語)である。
メムリスタとは、
電気的状態を「記憶する」素子のことだ。
チームはシリコンの代わりに、
ジオバクター・スルフレデュセンス
(Geobacter sulfurreducens)という
細菌から得たタンパク質ナノワイヤ
(タンパク質繊維)を用いてこれを作製した。
これらのナノワイヤは、
低電圧で自然に電荷を移動させる。
UMassのアプローチは、
テック大手が取り組むものとは大きく異なる。
インテルのロイヒ(Loihi)チップやIBMの
トゥルーノース(TrueNorth)は、
完全にシリコンで構築された
ニューロモーフィック・プラットフォームだ。
数千個のトランジスターでニューロンを模擬するが、
発火電圧は依然として生体よりはるかに高い。
これに対し、
UMassは生物学的特性を使った近道を採用した。
足りなかったピースがはまったのは2年前である。
大学院生のシュアイ・フーが、
ナノワイヤ・メムリスタを、
実際のニューロンの充放電の仕方を模倣する
単純なRC回路(抵抗とコンデンサを使った回路)
に接続したときだ。
「当時は、それを人工ニューロンの
構築にどう使えるのか、
あまり手がかりがありませんでした」と、
UMass応用生命科学研究所/
電気・コンピュータ工学科の研究者で
准教授のジュン・ヤオは振り返る。
この取り組みの成果は、
1度きりのバーストではなく、
再現性のある電圧スパイクだ。
実務上、これは脳と同様に、
ある人工ニューロンを次のニューロンの
引き金にできることを意味する。
この設計は、
チップ工場で用いられる標準的な
CMOSプロセスで製造可能である。
その点で、
特別な設備を要する量子デバイスや
フォトニクス・デバイスとは異なる。
ただしスケール化は依然として難しい。
タンパク質ナノワイヤは、
細菌によって生産し、精製し、
チップ上に配置しなければならない。
ヤオのグループは
エネルギーハーベスティング・デバイス
(環境中のエネルギーを電力に変換する装置)で
これを実施してきたが、
産業規模での一貫性は未証明だ。
これに比べ、
インテルやIBMはシリコン製のニューロンを
数百万単位で容易に製造できるが、
生体の電圧レンジにはまだ到達していない。
UMassは電圧とエネルギーの面で
生物学的忠実度を実現することでこの
関係を逆転させたが、
その代わりに材料面の課題が厳しい。
生体レベルの低エネルギー
このデバイスは、
1回のスパイク当たり数ピコジュールで発火できる。
これは、
通常0.3〜100ピコジュールを用いる
生体ニューロンに非常に近い。
これは理論値ではなく実測値だ。
回路の電圧と電流の測定がその主張を裏付ける。
この効率こそが、
インテルやIBM、BrainChip(ブレインチップ)のような
スタートアップを含む企業が
ニューロモーフィック・コンピューティングに
注目する理由である。
人間の脳は約20ワットで動作するのに対し、
同じ仕事をするデータセンターは
メガワット単位の電力を消費する。
しかしヤオは、
エネルギーだけがすべてではないと警告する。
「重要なのは、単一の
人工ニューロンのエネルギーだけではありません。
同様の方法でネットワークとして
接続することも必要です。
私たちはまだそこには
到達していません」と述べる。
純粋に電子信号のみに依存する
既存の商用ニューロモーフィック・チップとは異なり、
UMassのニューロンは化学にも応答できる。
チームは回路にナトリウムとドーパミンの
センサーを組み込んだ。
ナトリウム濃度は発火頻度を着実に押し上げた。
ドーパミンは
「アンビポーラ効果(両極性効果)」を
引き起こし、
低濃度では発火が増加し、
高濃度では低下した。
これは私たちの生物学が
行っていることにほかならない。
私たちのニューロンは化学信号に基づいて
発火を調整する。
UMassは、
それがハードウェアでも可能であることを示した。
ただし現時点では限られた分子に対してのみだ。
より広範なセンシングには、
新たな表面処理が必要になる。
同グループは、
このニューロンが生体組織と
接続できることも証明した。
培養皿内の心筋細胞に接続したところ、
人工ニューロンは細胞の通常の
拍動(0.4Hz)では静かなままだった。
ノルエピネフリンにより細胞の拍動が
速くなる(0.6Hz)と、
人工ニューロンは同期して発火した。
「現在のハードルは、
ニューロン信号の振幅全体を
捉える能力がないことです。
これはバイオセンシング分野で
知られた課題です」とヤオは語る。
人工ニューロンは信号を処理できる。
ボトルネックは、
それを拾い上げるセンサー側にある。
このデバイスは、
実際のニューロンと同様に、
発火に小さな変動を示す。
確率的計算に役立つプラス要素と見る研究者もいれば、
管理すべきノイズと見る研究者もいる。
UMassは、発火率が高いほど変動が低下することを見いだした。
これは生体の挙動を反映している。
これが機械学習に有用かどうかは、
システム設計に依存する。
今後の道筋
現時点で最も明確な応用は、
ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)や
超人的なAIではない。
医療診断、創薬スクリーニング、毒性試験など、
少数の人工ニューロンが細胞信号を
直接解釈できるニッチな
バイオセンシング・プラットフォームである。
今後10年で事態はどこへ向かうのか。
「10年という時間は、
私たちにあまりにも多くの驚きをもたらし得ます」と
ヤオは説明する。
「10年前を考えてみれば、
ChatGPTのようなAIを想像すらできなかったでしょう。
だから私は、大きな希望と
『何でも可能だ』という信念を抱いて
進みたいと思います。
そうでしょう?」。